はじめに
本稿は、世界最大のサーモン養殖生産国であるノルウェーの養殖業について、その歴史的発展と経済的側面を分析するものである。近年、日本でもサーモン養殖が注目を集め、各地でブランドサーモン養殖などの新たな取り組みが始まっているが、その発展形態はノルウェーとは異なる道を歩んでいる。ノルウェーのサーモン養殖業は、フィヨルドという特殊な地理的環境を活かした海面養殖から始まり、約半世紀にわたる発展の中で数々の技術革新、産業政策、環境課題との調和を経験してきた。この豊富な経験から日本が学べる点は多い。
なお、本稿ではサーモン養殖の技術的側面については詳細に取り扱わないことをあらかじめお断りしておく。著者は経済学が専門であり、養殖技術については詳しくない。養殖技術については専門誌や書籍で多く取り上げられており、また水産振興でも金子(2020)[1]がノルウェーの養殖技術について詳しく解説している。本稿では主に経済的・政策的側面に焦点を当てる。
特に本稿では、経済学的な視点からノルウェーサーモン養殖業を分析することで、環境と経済のバランスをとった持続可能な発展のための戦略や政策的示唆を提供することを目的としている。近年白熱している資源レント税の議論や環境規制の経済的インパクト、産業構造の変化など、経済学的フレームワークを用いた分析を通じて、日本の養殖業界が直面する課題への応用可能性を探る。
本稿は以下のように構成される。まず「経済的な観点から見たノルウェーサーモン養殖業の概観」では、グローバルな水産物需給の中でのノルウェーサーモン産業の位置づけを分析する。FAOのデータが示すように、世界的な水産物消費の増加と養殖生産の拡大という文脈において、サーモンは高い需要と限られた供給源という特徴から大きな経済的価値を生み出している。また、少数の大規模企業によって寡占化されているという、ノルウェーのサーモン養殖業界の特徴的な産業構造についても概説する。
続く「ノルウェーサーモン養殖の略史」では、19世紀末からの養殖の試みとその失敗、1960年代の海面養殖への移行、1970年代のライセンス制度の導入、1980年代の急成長期、そして1990年代以降の業界再編期までの歴史的経緯を詳述する。特に、小規模養殖業者から始まった産業が政府の規制と市場の変化によって大規模企業中心へと変貌を遂げた過程と、国際的な貿易摩擦や「プロジェクト・ジャパン」に代表される市場開拓の歴史に焦点を当てる。ノルウェーの養殖業が現在のような少数大規模の産業であることが、最初からそうではなかったという事実と発展過程を理解していただけると幸いである。
「環境問題と規制」のセクションでは、環境経済学における外部性の概念を基礎に、サーモン養殖が直面する環境問題と規制の進化を分析する。フィッシュミール・トラップ、有機廃棄物、抗生物質の使用、そして近年特に問題となっているサケジラミ問題について、それぞれの経済的側面と政策的対応を考察する。特に「信号機システム」などの特有の規制手法とその効果について議論する。
「養殖における資源レントと税」では、経済学的な資源レントの概念を解説し、ノルウェーが2022年に導入した資源レント税の背景と論理を分析する。石油産業など他の資源産業における課税との比較や、資源レント税をめぐる養殖業界、地域コミュニティ、中央政府の三者間の政治的対立構造を明らかにし、政策形成過程における政治経済学的側面についても議論する。
最後の「現在の論点」では、陸上養殖や沖合養殖など新たな生産方式の経済的合理性と将来性を検討する。特に、ライセンス価格の高騰や環境規制の強化によって、従来は高コストとされてきた陸上養殖が競争力を持ち始めている背景や、ノルウェー企業による日本を含む世界各地での陸上養殖展開の戦略的意義を考察する。また、2050年までに生産量を3〜4倍に増加させるというノルウェーの野心的な目標と、それを実現するための沖合養殖の可能性と課題についても検討する。
これらの分析を通じて、日本の養殖業が直面している技術的・経済的・環境的課題に対する示唆を得るとともに、持続可能で競争力のある養殖産業の発展に向けた政策的含意を提示したい。ノルウェーの経験から学ぶことで、日本独自の文脈に適した養殖業の発展モデルを構築する一助となることを期待する。
阿部 景太(あべ けいた)
1986年9月生まれ。兵庫県出身。関西学院大学総合政策学部卒業、北海道大学大学院環境科学院修士課程修了、ブリティッシュコロンビア大学経済学研究科修了(M.A.)、ワシントン大学経済学研究科修了(Ph.D.)。ノルウェー経済高等学院(Norwegian School of Economics)経済学研究科研究員、同応用研究所研究員を経て2022年9月より武蔵大学経済学部准教授、2025年4月から現職。岩手大学農学部客員准教授を兼任。
専門は資源経済学、環境経済学、応用計量経済学。経済学の理論・実証手法を応用して、日本・アメリカ・ノルウェーなどの漁業を対象に漁業者行動や、資源管理政策の効果や影響を経済的・社会的側面から研究している。
北米水産経済学会(NAAFE)最優秀学生論文賞(2017)、日本水産学会論文賞(2022)、環境経済・政策学会奨励賞(2023)。
- [1] 金子貴臣. ノルウェーにおける最先端養殖技術 —現在と将来—. 水産振興. 2020;620:.


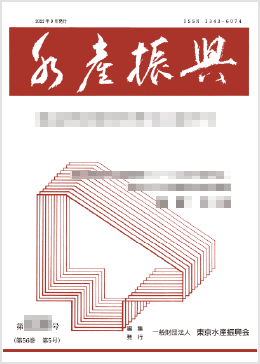 水産振興 649号
水産振興 649号