1. はじめに
2023年8月24日、東京電力福島第一原子力発電所の構内からALPS処理水が海に希釈処理の上排水された。ALPS処理水は、原子炉建屋に流入する地下水が東日本大震災後に起こった事故により発生した燃料デブリに触れて放射能汚染水となったものをALPSにより放射性物質を除去したものである。トリチウムだけが除去できないが、十分に希釈すれば排水をしても生態系や人間の人体に対する影響はほぼないということから、政府が放水をするとした。漁業界や地元福島県の他、東北の消費者団体なども海洋放出には反対姿勢を貫いたが、政府は、風評被害が生じないような対策、諸外国に理解を得るための行動をとり、風評被害が生じた場合にさまざまな対策を採るとして強行した。
ALPS処理水の海洋放出後の国内状況は、政府の風評対策が功を奏したこともあり、東日本大震災直後のような東北産水産物の安全性への不安をあおるマスメディアの報道や安全性を疑う情報発信は限定的であった。そのことから、国内の消費者が買い控えして、販売不振となったという漁業者や水産加工業者は全くいなかったわけではないがほとんど見受けられなかった。また海洋放出直後は「食べて応援」による需要拡大促進対策などが行われ、販売そのものは好調であり、小売価格は物価高騰と併行して下がるどころか上がり、ある意味、海洋放出の影響はなかったように見られた。
しかし、海外は違った。日本政府の東京電力福島第一原発の汚染水対策に対して、欧米諸国は理解を示したものの、そのような国ばかりではなかった。科学的に安全であるということが国際的に通じるというものでないことがあらわになった。それまでも1都8県の食品すべての禁輸措置を執ってきた中国、福島県水産物の禁輸措置を執ってきたマカオ、福島県の水産物以外の食品の禁輸措置を執ってきた香港、日本産食品に検査証明書の添付を課していたロシアなどが慎重な態度をとり、海洋放出後日本産水産物に対して禁輸措置を強化するとした。実際、実施後、措置内容は異なるものの、それぞれ禁輸措置を強化した。韓国は、尹大統領が親日派だったことから、ALPS処理水の海洋放出に対する理解を示したが、2013年以来、すでに福島県や宮城県などの水産物の禁輸措置を執っており、それはいまだ解除には至っていない。そのことから、台湾を除く近隣諸国・地域で東北産水産物に対する安全性の理解が得られていない状況で、海洋放出が実施されたことになる。
周知のように中国とロシアは日本産水産物の全面禁輸措置を執り、香港、マカオは禁輸措置の枠を広げた。海洋放出は国内の消費には影響を与えなかったが、そのことが水産業界にさまざまな影響を及ぼしている。
ALPS処理水の海洋放出が与えた損害などの影響について今のところ政府発表はない。理由はわからないが、筆者の経験からすると、その特定はかなり困難であり、推定や前年度との比較でしか表すことしかできない。なぜなら、本来の損害は、海洋放出がなかった場合とあった場合を比較しなければならないが、実態はどちらかだけなので、厳密な分析はできないからである。
そこで、本報告は、海洋放出の前後1年の水産物貿易の比較から、そのインパクトを考察してみる。
結論から述べると、次のように整理できる。海洋放出後はそれまでの円安基調がさらに強まり、輸出競争力が強まり需要拡大局面であった。しかし、日本産水産物の輸出額は大きく減った。それは禁輸措置を執った中国や香港の影響が大きいが、それ以外の輸出主要国でも輸出額は増えず、むしろ減った国も少なくない(真珠など水産宝飾品を除く)。禁輸措置を執っていない国では貿易額の上昇が見込めたはずではあるが、そうした現象が見られなかったのは、中国の禁輸措置の影響により輸出用水産物が過剰供給状態となり国際相場が下がったこと、華僑経済とのつながりが強いエリアで中国本国の対応に併せて一時的でも日本産水産物への忌避反応が起こった可能性が挙げられる。


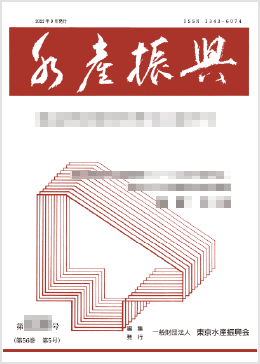 水産振興 647号
水産振興 647号