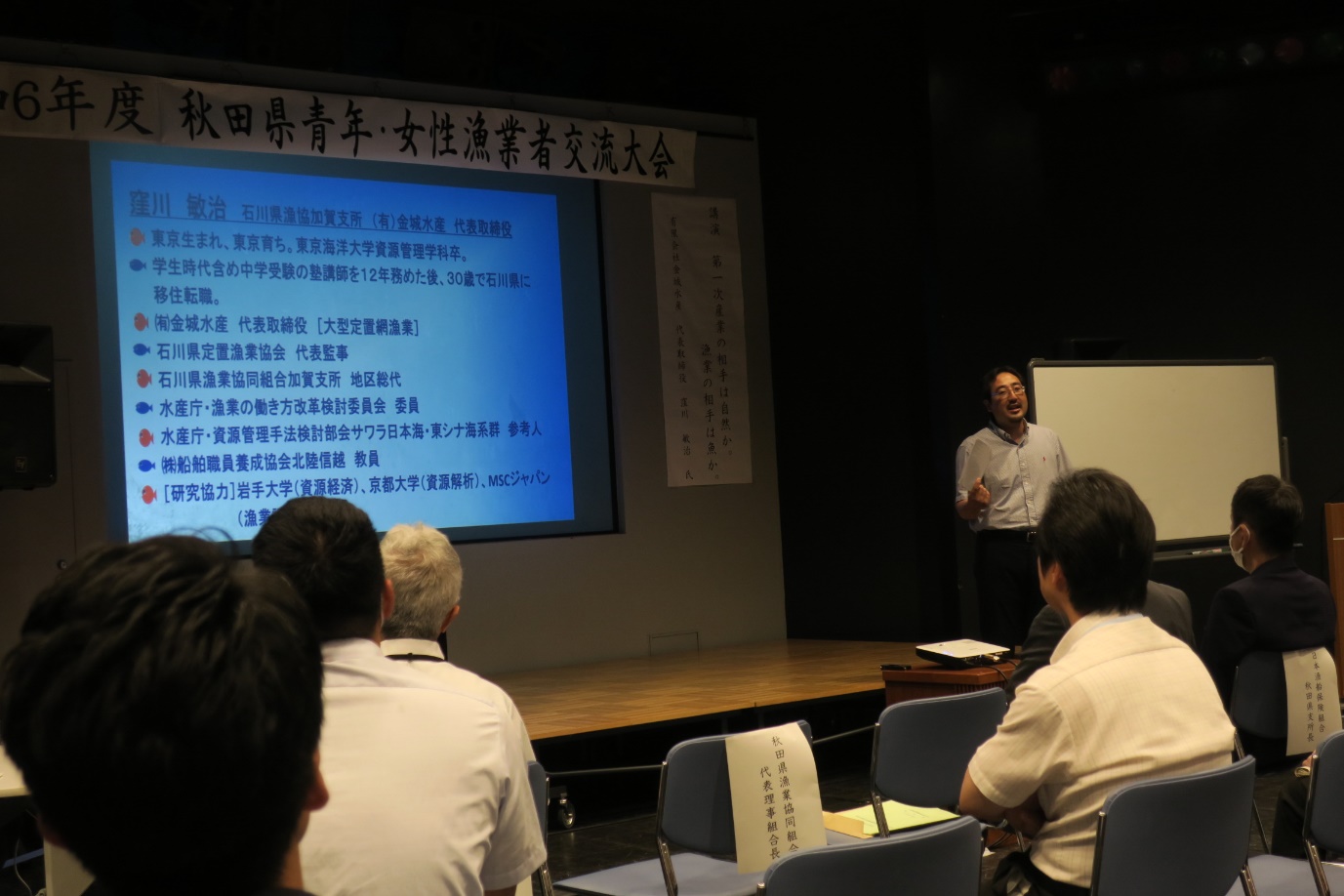
(水産経済新聞社提供)
秋田県の漁業の現状と問題点を事前に県の水産漁港課に聞くと、8項目が挙がってきた。そのうち4点は石川県の港でも起きているが、問題にはなっていないことだった。
4点とは、小規模の個人経営体が多い、セリ・入札が夕方、浜の仲買人や加工業者が少ない、だ。なぜ石川でさほど問題とされないことが秋田で問題視されるのか。強い違和感を覚えたため、県の見立ては現場に添っているのか、独自にヒアリングを行った。秋田の漁業者2人、漁業コンサル1人、漁協職員1人、卸1人、県外卸1人、県内の仲卸2人、知り合いの一般市民1人に「問題点」を聞いてみた。
まず、漁業者は周りからどうみられているか。「過去の自分と自分の浜しかみない」「意識が低い」「勉強不足」「秋田県人が魚食べないというのは言い訳」「市場・仲買の努力が伝わってない」「自己満足」「仲買の意見を聞かない」「仲買は敵」「変わろうとしない」「安い理由を聞かないでただ文句」「意思疎通がない」「情報を出さない」「流通のことを全然分かっていない」「仲買の付ける値段に疑心暗鬼」「獲ってきて出して終わり」などと言われている。
漁協・市場はどうか。「機能が弱い」「横流しするだけ」「やる気ない」「支所ごとバラバラ」「指導力がない」「まるっきり変わろうとしない」「頭が固い」「主張はするけど動かない」「県はやろうとしているが漁協は仕事しない」「若い漁業者と仲買が連携しようとしても漁協が間に入ってきて話が進まない」「意思疎通がない」「行きあたりばったり、時に任せてという現状」「新しいことを考えようとしない」「仲買が意見しても考えない」「与えられた仕事をやるだけ」「おじいさんたちが主導権を取りたい」「若手の意見が門前払い」「おじいさんに問題意識がない」。
仲買には、「大漁物が手に負えない」「自分たちがよければ」「人にもうかってもらっては困る」「意思疎通がない」「漁業者と敵対」「仲買がもうけているのでは」で、比較的、仲買に対する意見は少なかった。
そして県の水産漁港課に対しては、「つなげる努力をしていない」「日頃から来たりしない」「バラバラにやっているのを放置」「熱意、関心なんてないんじゃないか」「資源量に問題のあるハタハタを一生懸命アピールして、ほかのよい魚が揚がっているのをアピールしない」「意思疎通がない」「大きな指針がない」「社会の変化に対応していない」「行きあたりばったり、時に任せてという現状」「流通を話に入れない」「新しいことを考えようとしない」「指導しない任せっきり」「漁業者しか向いていない」「構造を変えていかないと」「漁業者・漁協・仲買の交通整理をせよ」「勉強不足(漁業者への取り組み・流通への取り組み)」「みんなの話を聞いて柔軟に対応して仕組みをつくれ」「音頭を取ったりしない」「何とかしなきゃという思いは伝わる」「アイデアが二番煎じ」、だった。
これらすべてが本当なら、水産秋田はとっくに崩壊している。再度、それぞれに「周りからこんなこと言われていますよ」と確認してみると、皆「そんなことはない。勘違いされている」と答えた。聞いていると、何とかして秋田の水産をよくしたいとする思いは皆もっており、同じ方向を向いていると思うのだが、なぜそんな誤解が生じてしまうのだろうか。そこに水産秋田の問題の本質がある。
(連載 第7回 へ続く)

