
八雲が描いた明治末期の焼津
ラフカディオ・ハーン(小泉八雲、以下八雲と略)は1897(明治30)年8月に初めて焼津を訪れてから1904(明治37)年9月に亡くなるまでの8年間で、計6回の夏を過ごしています。
波が荒く、岸からすぐに深くなる焼津の海岸は海水浴向きではありませんでしたが、水泳が得意だった八雲はこの海をとても気に入りました。
このころ焼津にはまだ船を係留したり陸揚げをする港湾施設はなく、黒石川の河口部を船溜まりとして使う程度で、大型漁船は沖合に停泊させ、伝馬船に荷を積みなおして陸へ運んでいました。焼津に漁港が整備されたのは第2次世界大戦後のことです。
漁船が動力化される直前の焼津の様子を八雲は生き生きと記しています。
《日本の、どの沿岸地方でも、——また同じ地方でも漁村が違えば——船や漁具の形は、その地方や部落によって異なっている。実際、せいぜい2、3マイル離れた部落がそれぞれ異なった形の網や船を製造し、それはあたかも、数千マイルも離れた民族の発明かと思われるくらい異なっている》
《焼津の大きな漁船は、この事実を例証している。この船は、焼津漁業の、日本全国へ鰹節を供給するという、その特殊条件に合うように考案されたもの。従ってそれは、非常な荒海を乗りきれるものでなければならなかった。このような船を海へ出したり引き上げたりするのは、大変な仕事である。が村中総出で手伝う。》
《一種の船曳き台をまたたく間にその場でこしらえるが、それは平たい木の枠を斜面に一列に並べるのである。それから、この枠の上に、平底船を長い綱を使って引き上げたり、引きずり下したりする。こうして、たった一隻の船を動かすのに、百人か、もっと多くの人々が——男も女も、そして子供たちまでも一緒になって、奇妙なもの悲しい歌に合わせ、引っぱっているのが見受けられる。台風が来るという時は、船はずっとうしろの町のなかまで運ばれる。そういう仕事を手伝うのは、なかなか面白い。》(『霊の日本』「焼津」)
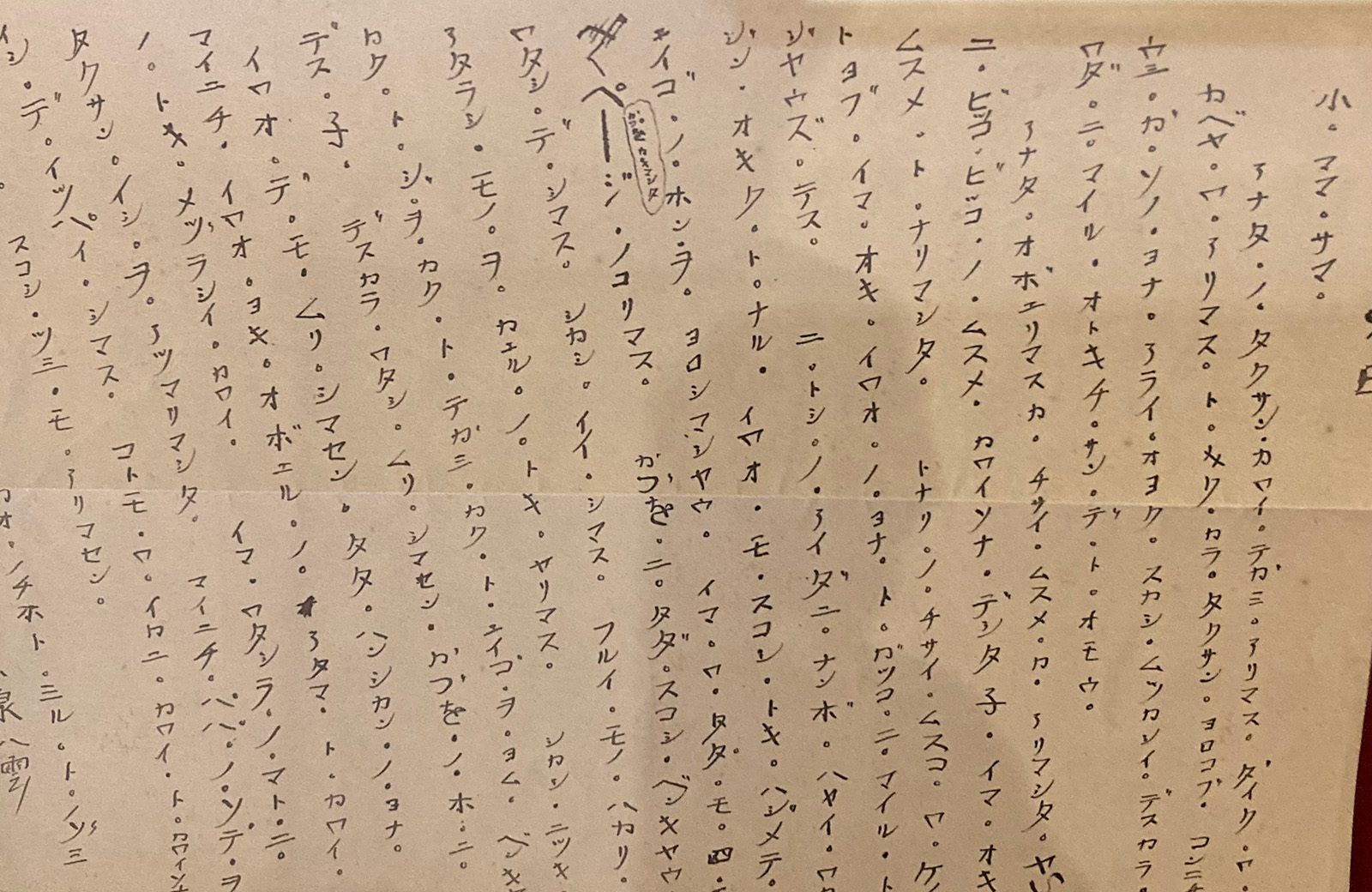
八丁櫓から動力船へ
焼津の漁船の特徴は高く反り上がった舳先を黒く塗った「黒みよし」と「八丁櫓」なのだそうです。
八丁櫓というのは船の右舷・左舷それぞれから四丁の櫓で漕ぎ進む船のことで、焼津にはこんな伝説が残っています。
徳川家康が焼津から久能(静岡市)まで船で渡るとき、最大七丁までと定められていた櫓を、緊急の場合ゆえ特別に八丁で漕ぐよう指示しました。これ以降、焼津の船だけに八丁櫓が許さるようになった……のだとか。
時代が明治に入ると、この八丁櫓のカツオ一本釣り漁船は櫓や帆を扱いながら伊豆七島の大島・神津島・三宅島近海まで出漁するようになり、明治20年代には無動力船ながら新しく発見された好漁場「銭洲」(神津島南西約36km)まで漁場を拡大していきます。
帰港までにかかる時間とカツオの鮮度低下を考えると無動力船ではここまでが限界でした。そこで漁船の動力化が急務となったのです。
遠くまで漁場を広げた理由のひとつは鰹節には脂肪分の少ない外洋のカツオのほうが適していたからです。カツオは駿河湾に入り湾内の豊富な餌を食べると3日ほどで脂肪分が増し、鰹節の原料には適さなくなるといわれていました。
今となっては駿河湾でカツオが獲れていたというのが驚きですね。
焼津旅行に同行したまだ幼い八雲の長男・一雄少年はのちにこう記しています。
《当時堤防の上から眺めていますと、沖の鰹船でキラキラ、キラキラと光って鰹が釣り上げられる様が見えたものです。》《父が行った頃の焼津にはまだ発動機船は一艘もなく、風向によっては一本の柱を立て、一枚の帆を張って走らせますが、大概の場合は逞しい腕の船子達が「エンヤエンヤ!」と声を揃え櫓拍子とって漕ぎ出す船ばかりでした。》(『父「八雲」を憶う』)
魚の鮮度を保つため、製氷機で作った氷が焼津で普及したのもこの頃です。
最初は仲買人たちの間で使われだし、漁船での使用は数年遅れたものの、氷漬けにしたカツオは氷を使わないものよりも3〜5割も高い値がついたため、1907年頃にはほとんどの漁船が氷を積むようになりました。
これは期せずして始まる漁船動力化時代への準備にもなったわけです。

学生にボイコットされる漱石
さて、1903(明治36)年3月。八雲は突然帝国大学を解任されます。
理由は、八雲は帰化していたにもかかわらずお雇い外国人並みに高給だったこと。本来、長期休暇取得の資格がない講師の身分にもかかわらず取得していたことなどの待遇面に加え、講義内容が大学側の求める英語学ではなく、英文学が中心だったこともあったようです。
「小泉先生がクビになるらしいぞ!」という情報が校内を駆け巡ります。八雲を敬愛していた学生たちは大学側に猛反発。「先生をやめさせるな!」と八雲の留任運動を始めます。
《これほど全英文科生がこぞって解雇に反対し、引留に熱心なのには、大学当局はびっくりした。そこで考えを翻して留任の再交渉をしたが、今度は難し屋のヘルンの方で臍を曲げてこれを拒否し、明治三十六年三月を以て辞職した。休みが終って、学校に出て、学生は皆がっかりした。留任が決まりそうだという噂が流れたので、一縷の希望をつないでいたのが断ち切られた。》(『早稲田百年史』)
こうなると八雲の後任は苦労するだろうと容易に想像できます。
後任となったのが夏目金之助、のちの夏目漱石だったことは前回触れました。このとき学生でのちに英文学者となった金子健二(昭和女子大学初代学長)は当時を振り返りこう書いています。
《夏目金之助とかいふ『ホトトギス』寄稿の田舎高等学校教授あがりの先生が、高等学校あたりで用ひられてゐる女の小説家の作をテキストに使用するといふのだから、われわれを馬鹿にしてゐると憤つたのも当然だ。》(『人間漱石』)
学生たちは授業をボイコットしたり、出席しても頬杖をついてノートを取らなかったり、あくびをしたり居眠りしたり……と夏目に総スカンをくらわせます。
こうなることは夏目もある程度察していたようで、妻・鏡子に不満を漏らしています。
《小泉先生は英文学の泰斗でもあり、又文豪として世界に響いたえらい方であるのに、自分のような駆け出しの書生上がりのものが、その後釜に据わったところで、とうていりっぱな講義ができるわけのものでもない。また学生が満足してくれる道理もない。》(『漱石の思い出』)

夏目は2年間の英国留学でストレスを募らせノイローゼとなり、日本では「夏目が発狂した」という噂が立ったほどですから、帰国後もまだ精神状態は不安定だったのでしょう。
悪いことは重なり、教え子が入水自殺した事件も「夏目が死に追いやった」と噂され、さらに夏目の心を脅かしました。
追い詰められた夏目は授業の休講が増え、家庭では暴力を振るうなどしてしばらく別居していますから、この年はどん底だったようです。
金之助から漱石へ
1904(明治37)年、焼津で夏を過ごし東京に戻った八雲は突然狭心症の発作で倒れ、帰らぬ人となります。54歳でした。
同じ頃、夏目の友人で俳人の高浜虚子は気晴らしにと夏目に創作活動を勧めました。夏目はペンネームを漱石とし、教師生活のかたわら38歳のときに書き上げたのが『吾輩は猫である』です。
この初めて書いた小説のなかで漱石は八雲について触れています。
《「僕のも大分神秘的で、故小泉八雲先生に話したら非常に受けるのだが、惜しい事に先生は永眠されたから、実のところ話す張合もないんだが、せっかくだから打ち開けるよ。》(『吾輩は猫である』)
その後も漱石は次々と作品を発表し、1908(明治41)年に著した小説『三四郎』でも、
《その時ポンチ絵の男は、死んだ小泉八雲先生は教員控室へはいるのがきらいで講義がすむといつでもこの周囲をぐるぐる回って歩いたんだと、あたかも小泉先生に教はったようなことを言った。》
と八雲を取り上げています。
八雲と漱石の共通点
それにしても八雲が死去すると、まるでバトンを渡すように漱石という作家が誕生したというのは興味深いではありませんか。
八雲と漱石の共通点は多く、2人はともに帝国大学で教える前に熊本の第五高等中学校で教鞭をとっています(ハーンは1891〜1894年、漱石は1896〜1900年)。
また、ともに肉親の愛情に乏しい生い立ちで、ハーンは6歳のときに母と生き別れ、大伯母に育てられました。漱石は1歳で養子に出され、9歳のときに実家に戻るも14歳で母を亡くしています。
妻がヒステリックだったというのも共通しています。
八雲の妻セツは激昂しやすいタイプだったらしく、長男の一雄は《私は幼少の頃、「一雄さんは大きくなつたらどんなお嫁さんを貰う?」と聞かれると「ヒステリーでない人」と答えた》と記しています。セツが主人公となる朝ドラ「ばけばけ」(2025年秋放送予定)ではどのように描かれるのでしょうか。
漱石も日記に妻鏡子を《妻はヒステリーに罹るくせがあったが、何か小言でもいうときっと厠の前で引っ繰り返ったり縁側で斃れたりする》と書き残しています。
そしてこんな共通点にも気がつきました。
16歳のときに事故で左眼を失明したハーンは写真を撮られるときは左か下を向き、左眼が写らないポーズをとっています。
漱石も3歳のときに患った天然瘡で右頬にアバタが残ったといわれ、そのためか顔の右側を隠したポーズの写真が多いのです(かつての千円札の正面を向いた肖像は修正写真)。

享保8年創業の鮮魚店「三四郎」。

