計算できるウニ養殖
コンブとの両輪が前提
5月中旬、東京も札幌市内も夏日を記録したこの日、北海道・釧路地区の浜中町の最高気温は14度C。空気が冷たい。
「3月末から始まった人工授精もそろそろ終盤です」。エゾバフンウニの種苗生産を担う浜中町ウニ種苗センターの羽生晃弘所長が、小型タンクが並ぶセンター内の一室を案内しながら教えてくれる。受精成功率はほぼ100%といわれているウニだが、種苗生産が容易なわけではない。道内のマニュアルに沿った管理でも、塩分濃度や光のわずかな変化が生育に影響する。センター完成前からウニ種苗生産に着手し、5年目を迎える羽生所長は「最初の3年間はトラブルの連続。幼生の段階で全滅させてしまったこともありますよ」と、苦笑いを浮かべる。

左から木下技術員と浜中町の東海林圭太水産課長
浜中町にウニ種苗生産センターが完成・稼働したのが2021年春。養殖ウニの安定生産実現に向けて町ぐるみで施設完成にこぎ着けた。同じ町内のJF散布漁協とJF浜中漁協を中心とする委員会が運営し、種苗生産にかかる費用は基本的に受益者の漁業者が負担している。現在、センターが年間に生産するウニ種苗は300万個。春に人工授精した種苗は最終的に屋外の水槽(7.5トン水槽30基)で5ミリサイズまで育て上げられ、その年の秋から冬にかけて150万個を放流用、残り150万個を養殖用として漁業者に等配分している。
町でウニ養殖を最初に始めたのは散布漁協。1992年の養殖部会の立ち上がりと同時に11人の漁業者が参加した。河口付近の静穏海域の漁場とはいえ、かごの形状や素材など数々の工夫を重ね養殖方法を確立。センターが完成する時にはウニ養殖を営む漁業者の数は29人まで増えた。一方、浜中漁協は散布に遅れること9年の2001年にウニ養殖を開始。現在56人の漁業者が参加するまでになっている。
センターが完成するまで、浜中町の漁業者は放流用や養殖用のウニ種苗を厚岸、羅臼などほかの地域から購入するしかなかった。センター建設は、ウニ養殖に手応えをつかみつつあった漁業者の悲願のもと、実現されたといっていい。
浜中町の養殖ウニの強みは何といっても、身入りに最適といわれるウニの餌になるコンブ(ナガコンブ)が豊富にある点だろう。ウニの種苗生産は他地域でも以前から行われているが、ほとんどが放流されているのが実態。浜中町にとって豊富な餌(コンブ)の存在が町のウニ養殖を「計算できる漁業」にしている。ただ、羽生所長が「次代を担う職員」と評する木下辰吉技術員は、全道で広がる温暖化の気配を目の当たりにし、「道内各地で高水温になることが増えた。これから何が起こるか分からない」と慎重だ。
忍び寄る温暖化リスク
道東釧路地区の沿岸には天然のナガコンブが繁茂している。成長すると15メートルにもなる長さからそう呼ばれ、煮ると軟らかくなるその葉質からコンブ巻きなど惣菜に重宝される。本格的な収穫の時期を前に間引いたコンブは軟らかく、棹を入れる前(漁の前)のコンブ「棹前昆布」としても珍重されている。
そんなナガコンブだが、昨年、生産量が例年より半減する事態が起きた。通常は夏場でも平均19、20度Cの海水温が23度Cまで上昇したことが原因のようだが、散布漁協の秋森新二組合長は「過去30年でこんなに獲れなかったのは初めて。本当に危機感を覚えた」と当時のショックを隠さない。幸い今年の生育は順調といい、中村雅人専務や、ウニ養殖を自ら営む村田準逸理事らとともにホッと胸をなで下ろしているが、危機感が消えたわけではない。
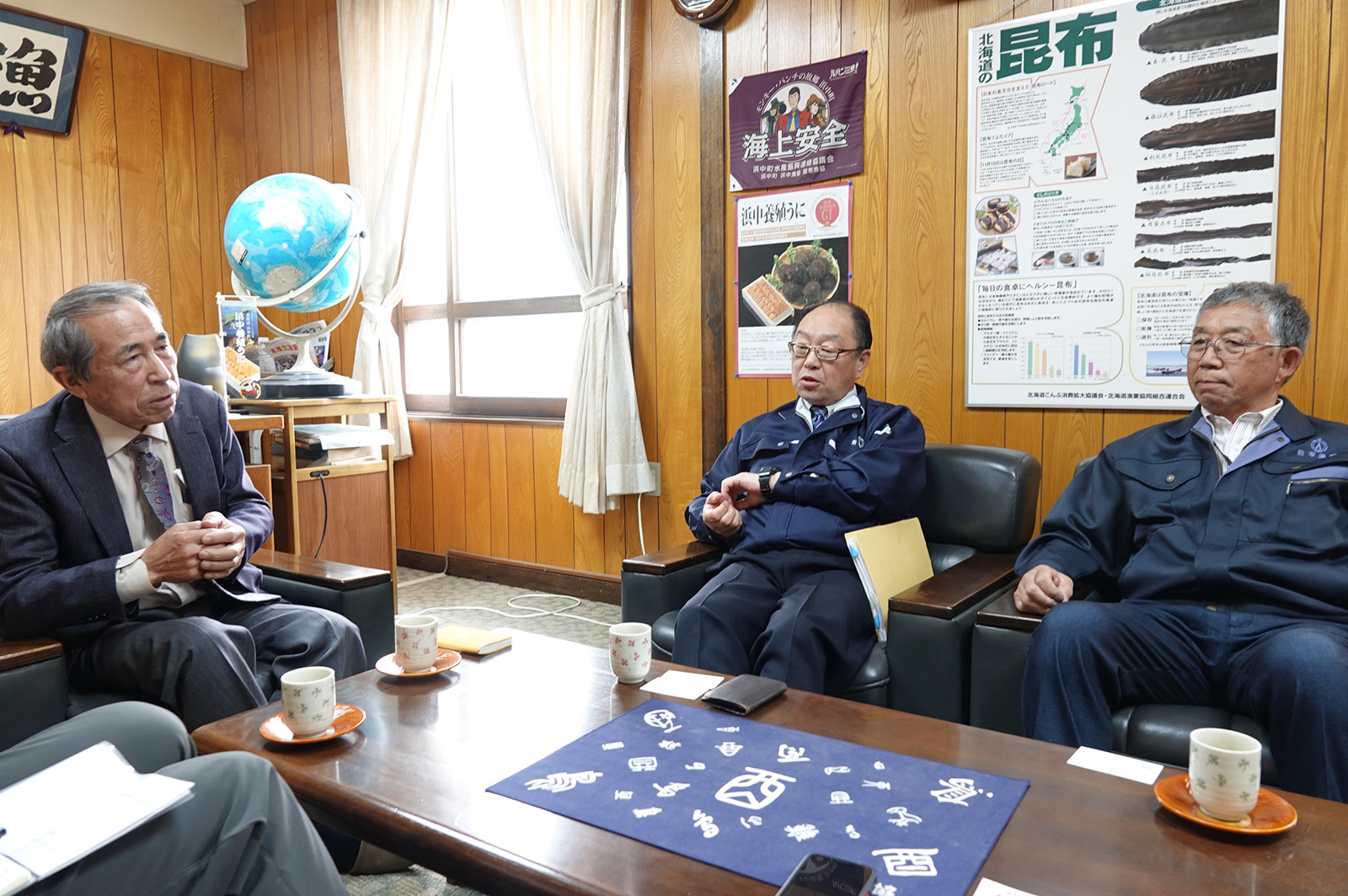
(左から秋森組合長、中村専務、村田理事)
近年、全道でも温暖化によるコンブ生産減少への懸念は強い。今年1月、道内で開催された北海道磯焼け対策連絡会議では、東北大学の吾妻行雄名誉教授が、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)のシナリオを基に北海道のコンブの将来を予測。最悪のシナリオの場合、道南のマコンブ、道日本海のホソメコンブとともに、「道東太平洋のナガコンブも2040年代に消失する」可能性を指摘し、浜中町のコンブ関係者を驚愕させた。
21年にも海の環境変化を象徴するような出来事が起きている。赤潮だ。ちょうどセンターが完成した年の秋で、道太平洋沿岸の天然ウニを一気に白化・死滅させ、ウニ以外の沿岸魚介類に斃死をもたらしたことで、「北海道でも赤潮?」とまだ記憶に新しい人も多いだろう。竣工直後のセンターでもウニ種苗が赤潮の被害に遭ったが、温暖化に起因するとみられる線状降水帯を伴う大雨の回数は増え、取水する海水の塩分濃度を一気に下げるなどのリスクは年々高まっている。
町ぐるみでブランドに

生産者とともに「浜中のウニ」を支えているのが加工業者だ。小川水産(株) もそのうちの1社で、地元はもとより道内各地や北方四島からウニを仕入れ加工している。地元の養殖ウニの年間取扱量は全体の約1割程度というが、小川雅弘社長は「浜中町の養殖ウニは、出始めの頃は評価されなかった時期もあったが、今は当社の製品の中でもトップブランド」とその品質の高さに太鼓判を押す。その理由についても「コンブだけを餌にしているため、濃厚な甘みとうま味をもち、色も粒も揃っている。身入りも他地域の天然物はせいぜい10~12%に対し、養殖ウニは15~20%と圧倒的にいい」と絶賛する。実際に加工されたウニを見ても、その差は歴然。コンブだけで育った証しの身色は、鮮やかで深みのあるオレンジがかった黄金色で揃い、見た目にも美しい。養殖は必要な時に必要なだけ手に入れられる強みもあり、生産者との連携でつくり上げた、まさに浜中の強力なブランド商品になっている。

小川水産はウニの加工法にもこだわりをみせる。いちばんのこだわりは水で、行き着いたのが「窒素水」の利用だ。
「よくミョウバンを使っているから苦みや雑味が出ると話す人もいるが、それは大きな間違い。ミョウバンは単に脱水の役割を果たしているだけで、ミョウバンで苦みが出ることはない。苦みの元はウニの洗浄不足。だからうちのウニに苦みはない」と自社ブランド「浜中 小川のうに」に自信をみせる。工場は浜中町の本社工場のほかに釧路にもあるが、総勢100人を超える従業員を雇用。インドネシアからの研修生も20人弱いるといい、人口約5,000人の町の雇用を支える存在になっている。

(小川水産本社工場で)
現在、「浜中養殖うに」は、その地域ならではの要因と結び付く知的財産として地理的表示(GI)に登録され、浜中町を代表する水産物の一つとして存在感を放っている。


