鹿児島県阿久根の水産業を支える海盛水産
鹿児島県阿久根市の漁業を支える存在として知られる「有限会社 海盛水産」。ここの定置網(つぼ網)部門を切り盛りするのが野村耕二郎さん(27歳、2025年6月時点)だ。漁師一家に生まれ育った耕二郎さんは、幼い頃から海を相手に生きる家族の姿を間近で見て育ち、自然と漁業の世界に魅せられてきた。
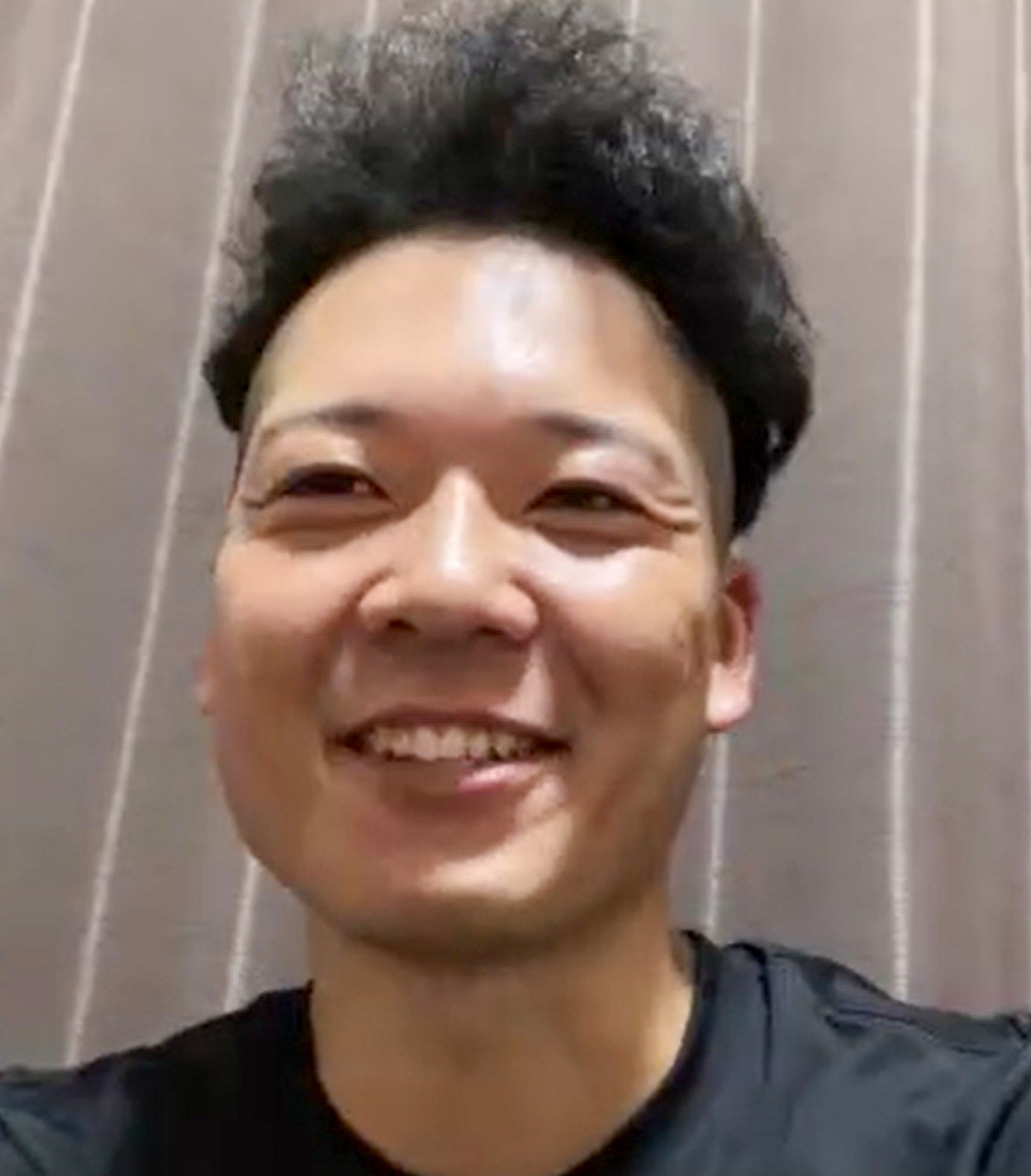
海盛水産は、耕二郎さんの祖父が1982年に兄弟で営んでいたまき網漁業から独立して創業した会社だ。アジ・サバ・イワシやタイなどを中心に獲る中型まき網船団を主力としている。2025年には日本初となる急速冷凍室を搭載した19トンのまき網漁船を新造船し、進水式には地域内外から多くの人々が集まり、地元の期待と業界からの注目の高さをうかがわせた。

海盛水産のまき網や定置網で水揚げした鮮魚は地元の産地市場へと出荷するだけでなく、自社直営の食堂「海盛丸食堂・うずしお館」や、水産加工品の製造にも活用しており、自社一貫体制を築いている。これらの取り組みにより、海盛水産は地域でも屈指の漁業経営体としての地位を確立している。
漁業は、いつもすぐそばにあった
そんな海盛水産に生まれた耕二郎さんにとって、幼い頃から漁業や海がとても身近な存在だった。将来は自分も漁業をやるんだろうな——そんな思いが、いつの間にか心の中に芽生えていたという。それは決して「継がなければいけない」という義務感ではなく、純粋に「漁業って楽しいなあ」と感じていたからだ。
父との小さな船旅が育てた「原風景」
小学生になった頃からは、遊びで父親に船に乗せてもらい、釣りにいくのが楽しみだった。時には自分で操船させてもらい、船を動かすおもしろさにも夢中になった。こうした体験の一つひとつが、耕二郎さんにとっての「漁業の原風景」として、今も心にしっかりと刻まれている。
中学生で初めて意識した漁業という「仕事」
中学生になると、耕二郎さんの中で漁業はただの「家の仕事」ではなく、「自分の将来の仕事」として真剣に意識し始めるようになっていた。中学を卒業したらすぐにでも漁師になりたい——いつしかそう思うようになっていた。しかし、親からは「高校には行きなさい」と言われ、地元の高校に進学することに。高校時代には一時期、美容師という全く別の職業にも惹かれ、進路に迷いが生じたこともあった。そんな中、高校の先生が山口県下関市にある水産大学校への進学を勧めてくれたことをきっかけに、耕二郎さんは「漁業の道をもっと深く学ぼう」と、大学への進学を決意した。
また、高校生活最後の長期休みには、実際に父と一緒にまき網の灯船に乗り込み、海の上で働く父の働く姿を間近でみた。「漁業ってやっぱりかっこいい!」という気持ちが再び芽生え、漁業への想いが再燃した。
知識と経験を積み重ねた大学時代
水産大学校では水産流通経営学科に入学し、実家を離れて一人暮らしをしながら、魚を獲ることだけでなく、その後どのように流通し、最終的にどのように消費者の食卓へと届くのか、水産業全体の流れを幅広く学んでいった。そして、そこには数多くの課題や、新たな可能性が広がっていることを知る。授業では、大学の先生から全国各地の先進的な取り組みを紹介してもらう機会もあり、大いに刺激を受けた。また、授業で学ぶだけでなく、自ら先生の研究室へ足を運び、いろいろな取組を紹介してもらうなど、積極的に知見を広げていった。中でも印象に残った事例には、他大学で学んでいた兄とともに自主的に現地視察に出かけるなど、意欲的に学びを深めていった。
さらに、大学の長期休みには地元に戻り、実家のまき網の網船に乗り、仕事体験を積み重ねていくことで、机上では学べないリアルな漁業に接し、学びを掘り下げていった。
魚の “その先” が知りたい
こうして充実した4年間の大学生活はあっという間に過ぎ、卒業後は迷うことなく地元の阿久根へ戻り、満を持して、家業である漁業の世界へと飛び込んだ。
実家に戻った耕二郎さんは、まき網船の網船に乗り込み、約10人の乗組員たちと共に毎朝海へ出る日々をスタートさせた。しかし、本格的に漁師としての道を歩み始める中で、耕二郎さんの中である疑問が芽生えてきた。
「自分たちが獲った魚は、その後どこへ運ばれ、誰が、どのように食べているのだろう?」
大学時代に学んだ水産物流通の知識が、今度は現場での “リアルな問い” としてよみがえってきた。魚の「その先」を自分の目で確かめたい。そんな想いから、耕二郎さんは一度網船を降り、もう一つの実家の拠点「うずしお館」で働き始めることを決意する。
魚を捌くところからの再スタート
うずしお館は、2002年に祖父が始めたもので、当時は地元産品を中心に販売しており、当初は鮮魚の取り扱いは少なかった。その後、2021年にリニューアルオープンしてからは、母親が中心となってお店を切り盛りするようになり、まき網の鮮魚販売にも力を入れていた。それまでほとんど魚を捌いたことがなかった耕二郎さんは、うずしお館の厨房で魚をさばくところから始めた。ひたすら魚を捌く日々。最初はぎこちなかった包丁さばきだが、経験を重ねるうちに上手くなり、今では父親からも「こいつはしっかり魚をつくれる(捌くことができる)もんね」と太鼓判を押されるまでに成長した。


定置網と食堂をつなぐ——若き漁師の想いを届ける新たな挑戦
そんなある日、父親から提案された。「使っていない定置網がある。お前、やってみるか」。そこで耕二郎さんは新たなる次の挑戦として、定置網を操業することを決意する。
最初は親戚と二人体制で定置網を操業していたが、半年後にはすべての工程—網入れ、水揚げ、出荷、網の手入れまでも—を耕二郎さん一人でこなすようになる。一人で操業し始めてから間もない頃、大漁に恵まれたあの時の興奮と喜びは今でも忘れられない。ブリ、スズキ、ヒラメ、タイ。いろいろな魚がとれる定置網は「めっちゃ楽しい!」

現在では、定置網で水揚げした魚のほとんどを、うずしお館へ運ぶ。定置網が始まってから、「海盛丸食堂・うずしお館」として、定置網で獲れた魚をメインにランチで提供するようになったのだ。水揚げした魚をすぐさま耕二郎さんは一匹ずつ丁寧に処理し、それをすぐにうずしお館へ運ぶ。そして母、妹、妻、パートスタッフがそれらを調理し、定置網の魚を中心としたランチを作る。
ある日、食べた人から「今まで青魚は食べられなかったけれど、ここのお店の青魚はとても美味しい」と声をかけられた。その言葉に、耕二郎さんは、いかに一匹ずつ丁寧に魚を処理することが大切か。そうした魚が、いかに人々を惹きつけるか。そうしたことを痛感している。耕二郎さんは、自分が定置網で獲った魚を食べる人を間近で見ることができるようになった今、自分の仕事に誇りとやりがいを強く感じている。
「ここに来ないと食べられない」——若き漁師が確信した価値
地元では今もなお、お裾分け文化が残っており、わざわざ魚を買いに来る人は多くない。ある意味で、阿久根は漁村ならではの助け合いや分かち合いの生活スタイルがしっかりと残っている地域だ。
しかし、一方でうずしお館は鹿児島市内から長島町という人気観光地へ向かう途中に位置しており、週末には多くのドライブ客が立ち寄る。「ここでしか食べられないものがある」。そんな特別な体験を提供できれば、人は足を止めてくれるはず。うずしお館で魚を提供する中で、耕二郎さんの中にこうした確信が芽生えた。耕二郎さんが自ら獲った魚を、この場所でしか味わえない一皿として提供する。それは、旅の途中で、ふと立ち寄った食堂で出会う地魚の味。それは、若き漁師の思いをのせた、ここでしか食べられない一皿になるはず。「これからは、うずしお館での“食”の提供こそが、漁業と地域を元気にする鍵になる」。そうした思いを強くしている。
筋肉で未来を切り拓く? “かっこいい漁師像” を目指して:耕二郎さんの意外な次の一歩
これからの漁業を支えていくために耕二郎さんが目指すのは、若い世代が「漁師になってみたい」と思えるような環境づくりだ。その第一歩として、「まずは漁師のイメージを変えていきたい」と語る。
どう変えていきたいのかと尋ねると、少し照れたような笑顔を浮かべながらも、真剣な表情でこう続けた。
「まずは、筋肉をつけてボディービルダーみたいな体になりたいですね。見た目から “かっこいい!” って思ってもらえるような存在になって、若い子たちから憧れられる漁師になりたいんです。そうすれば、僕のあとに続く次世代の人たちも、“自分も漁師になってみようかな” って思ってくれるかもしれないから」。
力強い体づくりの先に見据えるのは、“かっこよくて、憧れられる漁師”。その姿を通じて、耕二郎さんは未来の仲間を迎え入れる準備を、着実に進めている。


