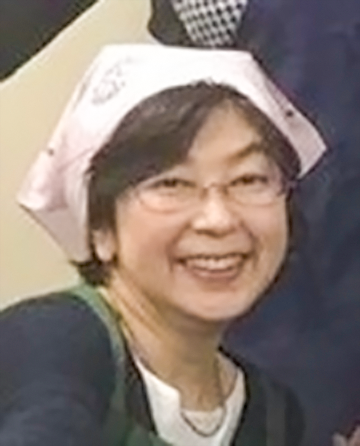大学時代、本州最西端のまちで地域おこしの活動にはまり、現在は本州最東端の岩手県宮古市重茂で漁師の妻となり、漁業に従事しながら地域おこし協力隊として観光振興にも関わる中村菜摘さん。今回は、ギラギラと地域おこしに奮闘する菜摘さんのお話をお聞きしました。
大学時代にはまった「地域おこし」
水産大学校の2年生の時に、先輩たちがまちおこしサークルを立ち上げるから一緒にやろう、と引っ張り込まれたのがきっかけで、立ち上げメンバーの一人としてサークル『吉見ガールズコレクション(YGC)』に参加しました。吉見の女性農家さんの農園で、新入生歓迎会のフラワーアレンジメント体験を企画したり、下関沖合底曳網漁業ブランド化協議会主催の連子鯛料理コンクールに、地元の女性たちと参加してレシピを考案したり。学校のある吉見の隣の吉母地区の自治会長さんから、吉母の地域おこしを手伝ってほしいとお話があって、地域の山の整備やイベント参加などもやりました。大学時代に、地域おこしにすっかりはまりました。YGCのメンバーは女性中心なのですが、山の整備などは力仕事も多いので、助っ人で男子学生も参加してくれました。夫とはYGCの活動がきっかけで知り合ったんです。

オーストラリア、本州四端制覇、そして重茂へ
私は端っこに縁があるんですよ。学生時代は本州最西端の地域に暮らしていました。今暮らしている重茂は本州最東端のまちです。青森県の大間は本州最北端、和歌山県串本町は本州最南端。この2か所にも立ち寄って、2022年に本州4端を制覇しました。
重茂に最初に行ったのは2018年。その後大学を卒業してからオーストラリアに渡り、2021年に帰国した後、宮古を再訪しました。2023年に結婚。宮古市の地域おこし協力隊として働き始めるとともに、漁業にも挑戦し始めました。地域おこし協力隊では、観光案内、誘客、宣伝などの仕事をしています。海外からの客船も寄港するので、通訳を頼まれることもあります。
豊かな重茂の漁業
重茂ではワカメやコンブ、ウニ、アワビ等の漁業が行われています。
早どれワカメ(養殖ワカメの間引き)は1月から2月。塩蔵ワカメは3月から4月。塩蔵コンブが5月から6月。干しコンブは6月から7月。干しコンブの作業は、早朝3時とか4時に始まります。水揚げされたコンブを1本1本洗濯ばさみで止めて、乾燥室で干していくという重労働で、この干し作業を初めてみた時は衝撃を受けました。ウニ漁は6月から8月。4時半頃に船に乗って漁場へ行きます。本州で一番最初に昇る朝陽を見ながら漁ができるのは、重茂ならではの特権です。重茂では、アワビの貝殻にウニを詰めて焼く、やきうにが名物になっています。ウニ漁がある時は、3時に起きて港へ行き、8時頃帰港します。そこから観光案内所へ行って観光協会の仕事をする、というハードスケジュールになります。タコ漁は10月からですが、漁期はほぼ周年です。アワビは11月から12月になります。夫の実家では、夫だけでなく義兄も重茂に戻って漁業に従事しています。
漁業ではないですが、9月から11月にかけては、マツタケやマイタケ、シイタケも採れます。これらも貴重な収入源です。

震災を風化させたくない
宮古市の地域おこしに関わる中で、今地域が抱えている課題の一つに東北大震災の記憶の風化ということがあるように感じます。東北大震災から14年経って、震災があったことに目をつぶろうとしている人が増えているように思うのです。けれど、日本一高い津波が重茂を襲った、このことは忘れてはいけないし、語り継ぐべきと考えています。東京などの大学生が毎年宮古に来るのですが、みんな震災のことを聞きたがります。宮古市田老地区では震災遺構が残されていて、観光を通して学ぶ防災というプログラムを作っています。
重茂の津波は真っ青な波だった
震災に関連していろいろな話を聞くようにしていますが、中でも印象的なのは、どこの地域でも津波は真っ黒な波なのに、重茂の津波だけは真っ青の波だった、という話です。重茂は全国屈指の石鹸推進地域です。JFで扱っている「わかしお石けん」の普及率が高く、香典返しもわかしお、というくらい定着しています。波の色は、合成洗剤を拒否し、石鹸運動を長年継続してきたことが一つの要因となっている、と考えられています。
今ある資源の活かし方を考えたい
地域の課題はほかにもあります。例えば、今そこにあるのに活かしきれていない資源をいかに活用していくか、ということもその一つです。卒業研究でナルトビエイの駆除、ということをテーマにしたのですが「駆除」ということに引っかかるものを感じていました。オーストラリアに留学したのは、この国が今ある物を活かすという方向性を大事にしているということがあったからです。駆除ではなく、保全することを勉強したいと思いました。
未利用茎わかめは宝物
活かしきれていない資源として、今注目しているのが茎ワカメです。ほとんどが燃料と人件費をかけて廃棄しているということを知って、納得いかない、という気持ちでモヤモヤしています。そこで、佃煮やさんに声掛けしたり、内陸の方でヤーコンを作っている所と何かコラボできないか検討したり、大学生に茎ワカメを使ったレシピ考案をお願いしたりと試行錯誤している所です。未利用茎ワカメをゼロにしたいし、何らかの商品化をすることで、無駄なく活用して収入にも結び付けばいいな、と思っています。
YGCで活動していた時、底曳網に入ってくる連子鯛がいわゆる未利用魚だったので、これに付加価値をつけようと、連子鯛を使った料理コンクールが開催され、地元の方々と一緒にレシピ開発をしたことがあるのですが、1匹丸ごと南蛮漬けにしたらおいしかったし、みんなでああでもないこうでもないと考えることがとても楽しかったという記憶が背景にあって、今は茎ワカメをどうにかしたいという思いにつながっています。未利用、という言葉には敏感に反応してしまうんです。
民泊と漁業体験
結婚に先立って、重茂の空き家を購入することになりました。賃貸で暮らすよりその方が安上がりだと判断したからですが、これがやたら部屋数の多い大きな家でして、そこで漠然とやりたいなぁ、と思っていた民泊をやることにしました。地元のおいしいものを食べてもらい、重茂の暮らしや漁業の体験ができる民泊です。その中で、震災や環境の話もできるといいな、と考えています。2023年は、私の妹や神奈川で私のオンライン塾に参加していた男の子に声をかけてきてもらいました。神奈川に戻った時にその男の子に会ったのですが、「将来、漁師になるのもありかも」と言ってくれたのがとても嬉しかった。何というか、ああ、こういうことだよな、と思ったんです。
2024年には、県が実施している若者のアイディアを実現するための支援事業などを活用して、大学生の漁業体験と民泊の1週間プログラムを実施しました。学生の体験を受け入れてくれる漁家も最初は3軒でしたが、2025年には昨年の様子を見ていた2軒の漁家が、新たにうちにも来てもらいたい、と希望を出してくれました。
漁業体験は、人手が足りない漁家のサポートにもなるし、地域の漁業に新しい風を吹かせるきっかけにもなると思います。普段できない本物の体験ができることは、来る人にとっても貴重なことなのではないでしょうか。


目標は、自分自身が観光資源になること
地域に興味を持ち続け、地域のために何かしたいと思えるのは、地域の人から自分がこの地域に必要とされていると感じられる、つまり自己有用感があるからだと思います。もう一つは、自分自身が感動しぃだっていうこともあるかもしれません。いろんなことにわぁ、すごい!という思いを持つ。それを人にも分けていきたい。感動をシェアしたい。そういう気持ちが漁業体験や民泊につながっている。本当は自分のことになると、すごく迷いがあります。オーストラリアに行く時も、岩手に嫁に行く、という時も。でも、そこに行った後の自分の在りたい姿を想像できれば、進んでいくことができる。重茂に行く時は、漁師になっているのもいいな、と思っていました。でも現場にきてみて、漁師の妻もいいかな、と今は思っています。行ってみてやってみて、違ったらまた別の方向に行けばいいかなとも思います。そうして自分自身もいろいろな体験を積み重ねていくことで、私自身が観光資源になれたらいいな。私がいるから重茂に来るっていう人が増えてほしいし、民泊と漁業体験で宮古をみんなの故郷にしてしまいたい!